【ユーザーインタビュー】 児童発達支援・放課後等デイサービス ののはな 様
デジリハって実際どんな施設で、どんな風に使われているんだろう?そんな疑問の声にお応えして、デジリハユーザーを紹介していきます!
今回は児童発達支援・放課後等デイサービス「ののはな」さんです!
施設管理者/児童指導員の松尾さん(中央)、施設管理者の久保さん(右)、機能訓練士の佐藤さん(左)にお話を伺いました!
ーー施設の特徴やスタッフの体制について教えてください!
松尾さん:「ののはな」では、毎日さまざまなプログラムを実施しています。たとえば、私は毎週木曜日に児童発達支援のプログラムを担当しています。
すべての職員が曜日ごとにプログラムを担当しており、その曜日に利用している子どもたちが月に1回はデジリハを体験できるように、1か月単位でプログラムを職員が考えています。
ののはな(逗子・山の根)は定員が20名と大規模なため、体験の待ち時間が長くならないように、スタッフ2〜3名に対して児童約6名程度の少人数入れ替え制でプログラムを行うことが多いです。
久保さん:施設の強みとしては、作業療法士、言語聴覚士、看護師、心理担当職員といった専門職が在籍していることですね。これは療育の質を高める大きなポイントだと思っています。
また、私たちはソーシャルスキルトレーニング(SST)にも力を入れている事業所で、多くの事業所では教材を使ってSSTを行うことが多いと思うのですが、「ののはな」では学校の授業と同じ45分間、グループで着席して取り組むスタイルをとっています。
さらに、集団プログラムと個別対応の両方に対応していることも特徴です。専任講師によるリトミックなども実施しており、幅広いアプローチで子どもたちを支援しています。
私自身は、2022年6月の開所時から運営に携わっており、管理者として全体のマネジメント業務を中心に担当しています。ただし、必要に応じて送迎や現場の支援に入ることもあり、日々子どもたちの様子にはできる限り目を配るようにしています。

ーーデジリハを導入したきっかけは?
松尾さん:「ののはな」は周囲に気軽に遊びに行ける公園が少なく、施設内でも子どもたちがのびのびと身体を動かせる十分なスペースを確保することが難しい環境です。そのため、「もっと身体を動かして、思い切り発散できる機会をつくってあげたい」と日々の支援の中で強く感じていました。
そんな中、2023年に開催された「介護・看護EXPO」内の「児童発達支援・放課後等デイサービスフェア」に何気なく足を運んだ際に、デジリハさんのブースに出会いました。実際にMoffバンドのアプリを体験させていただき、「これは面白い!」「子どもたちも楽しめそう」と、強く印象に残りました。
ののはなに来てくれている子どもたちは、マインクラフトやタブレット、ゲームが大好きなので、デジリハを気に入ってくれるのではないか?デジリハであれば、室内の限られたスペースでも身体を思い切り動かすことができ、運動に苦手意識があるお子さんでも、楽しみながら身体の動きをコントロールする力を育てられるのではないか?
また、当時神奈川県内ではまだ導入例が少なく、ののはなの特色にもなると思い、「この施設にはデジリハがぴったりなのではないか」と、社長に導入の打診をして快くOKをいただきました。まずはデモ体験を経て、HOKUYOセンサーの導入からスタートしました!
――デジリハは日々どのように活用されていますか?
松尾さん:各曜日のプログラムにおいて、月1回程度のペースでデジリハを取り入れています(※水・木曜日はSSTを実施しているため、デジリハは長期休み中に活用)。
放課後等デイサービスでは、6名前後の児童が15〜20分ずつ交代制で参加し、児童発達支援では集団プログラムやST(言語聴覚士)による個別プログラムの中で活用しています。
具体的な活用例としては、「そらの水族館」や「忍者でドロン!」などのアプリを集団療育の中で取り入れています。

佐藤さん:集団療育でデジリハを活用する際、どうしても「待ち時間」が発生しますが、それが結果的に「順番を待つ」、「交代する」といった行動の練習の機会にもなっていると感じます。デジリハは楽しいので、子どもたちのモチベーションにつながっていて、自発的にルールを守ろうとする姿が見られます。
学校で学んだことかもしれませんが、それを自然と実践している姿を見ると、ソーシャルスキルの育成にもつながっていると実感します。

久保さん:当施設ではプログラミング教育も取り入れていて、マインクラフトなどのツールを使っています。やっぱり「マイクラ」と聞くだけで、子どもたちの反応が全然違うんです(笑)。
私たちは「楽しい」と「療育」のバランスをとても大切にしている施設なので、まずは「楽しい」と思える体験を通じて、そこから自然に学びが広がっていくことを大事にしています。その意味でも、デジリハは施設の方針とも非常にマッチしていると感じています。
佐藤さん:あと、「忍者でドロン!」はグループ分けをしてチーム戦の形式で取り組んだこともありました。チームでの協力や応援といった関わりも自然に生まれ、非常に盛り上がりました。
ーーどのような視点を意識して活用されていますか?
松尾さん:子どもたちのほうが職員よりも早くアプリの調整方法を覚えていて、デジタルが得意な子が苦手な職員に操作を教えてくれる場面もありました。そこで私のプログラムでは、パソコンやゲームが得意な子どもたちに“サポーター”として協力してもらい、アプリの設定や操作をお願いすることもあります。
これは、パソコンやマウスの操作練習にもなりますし、「お友だちの準備ができているかを見てから声をかけてスタートする」など、周囲を見る力や他者への配慮にもつながっています。
なにより、子どもたちが“得意なことで活躍し、認められる経験”を積むことを大切にしたいと思っています。
また、職員によっては、タッチ棒を作ったり、絵カードやボールを活用したりと、それぞれのアイデアを自由に取り入れて使っています。他の職員の工夫から新たなひらめきを得たり、アイテムを改良したりと、日々アップデートが重ねられています。
私自身も、他施設や学校でのデジリハの活用事例を積極的にチェックしていて、そこからヒントをもらいながら、「ののはな」の子どもたちに合ったプログラムを考えるようにしています。
ーー子どもたちにどんな変化や成長が見られましたか?
松尾さん:デモ導入時から感じていたのですが、順番を待つのが苦手だった子どもたちが、デジリハではメリハリを持って楽しんでいる姿がとても印象的でした。
最初は自由に触って遊んでいた子どもたちも、次第に「タイマーが鳴ったら交代」「1回タッチしたら後ろに並ぶ」「リレー形式で挑戦する」など、遊び方のルールを覚え、個人からペア、グループへと自然と協力の形が生まれてきました。

異なる学年でチームを組んだ時には、「こっちだよ!」「前に進もう!」と子ども同士で声をかけ合ったり、待っている間には相手チームを応援したりと、ポジティブなコミュニケーションが増えてきたのも印象的でした。
勝ち負けの受け入れも大事な経験なので、事前に「ゲームだから負けても怒らない」ことや、「そんな時どんな気持ちになる?どんな声かけができるかな?」ということをみんなで話し合う時間も設けています。
また、児童発達支援や低学年のプログラムでは、ただ自由に触って遊ぶだけでなく、水族館の絵カードや文字カードを提示して対応するなど、マッチングや記憶の要素を取り入れた活動もしています。
何度もデジリハを体験していく中で、わくわくしながらも、自分の番が来るまできちんと椅子に座って待つという姿も増えてきました。
佐藤さん:来所している子どもたちの中には、視野が部分的にしか見えていないお子さんも少なくありません。そういった子どもたちにとって、HOKUYOを活用したデジリハのプログラムは、意識的に「全体を見る」という動作が自然と促されるため、とても有効な療育になっていると感じています。楽しみながら、視野を広げていく経験ができるのは、デジリハならではの良さですね。

ーー導入してよかったと感じることやご家族の反応は?
佐藤さん:僕自身、ののはなに入るまではずっと放課後等デイサービスや児童発達支援の現場にいました。デジリハを触るようになって、普段あまり関わることのなかった職員同士が一緒に取り組むことで、自然とコミュニケーションが増えてきたなと感じます。そういった副次的な効果もすごく大きいと感じています。
松尾さん:応募者の面接の際に、デジリハのことを話すと「面白そうですね」と関心を示してくださる方もいて、新しい取り組みにポジティブな印象を持ってもらえているのが伝わってきます。
また、現場の職員からは「プログラムを考える負担が少し減った」という声もありますし、急な欠員時に「デジリハで対応できた」ということもありました。柔軟に活用できるツールとして、とても助けられています。
松尾さん:保護者会でデジリハの体験会を行ったのですが、とても好評でした!「家ではできないような貴重な体験をさせてくれてありがとう」と、記録へのコメントで伝えてくださる保護者の方もいて、保護者の方々にも喜ばれている実感があります。
久保さん:「楽しそうに遊んでいる姿が見られて良かった」と、ポジティブな声がたくさん届いています。お子さんの笑顔を見て、安心される方も多いですね。

ーーデジリハを活用する上で、工夫されていることはありますか?
佐藤さん:スタッフが積極的に声をかけたり、お手本を見せたり、「このカードに触ってみよう!」と誘導したりと、関わり方を工夫しています。
「そらの水族館」アプリひとつでも、いろいろな使い方があるんです。例えば、「ひらがなが意外と読めている」「『クジラに触ってみて』と伝えたら、ちゃんと理解して動いてくれた」など、子どもたちの“気付き”や“成長”が見える瞬間がたくさんあります。
ーー最後に大切にされているお子さんへの接し方や療育の考え方があれば教えてください。
久保さん:私は「将来、社会に出て働く大人になる」という視点を常に意識しています。だからこそ、今のうちから言葉遣いや振る舞いなど、社会で必要となる力を少しずつ練習していくことが大切だと考えています。
その土台にあるのは、「たくさん褒めること」、「認めること」です。子どもたちの小さな頑張りや変化に気づき、それをしっかりと言葉で伝えること。それが子どもたちの自信や意欲につながっていくと信じています。
ののはなでは、こうした日々の積み重ねの中で成功体験を重ね、園や学校、家庭生活での困りごとが少しでも減るように支援していきたいと考えています。
そして、ののはなのロゴに込められた「子どもたちの笑顔の花を“幸せを運ぶ青い鳥”によって社会に届けられるように」という思いを、日々の実践の中で形にしていきます。
ののはなに関わるすべての人が「ここは楽しい」と感じられるような環境づくりを、これからも大切にしていきたいです。
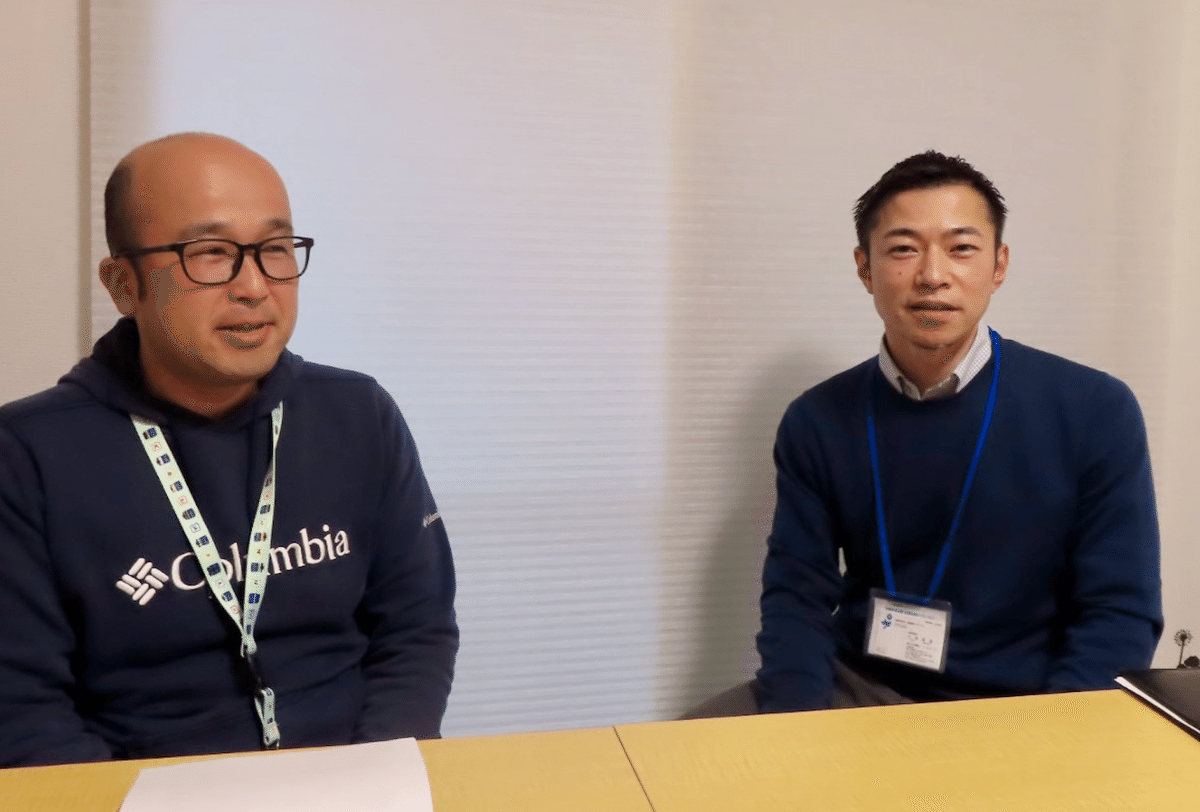
更新日:2025年7月7日
記事一覧に戻る